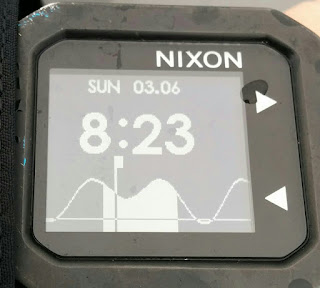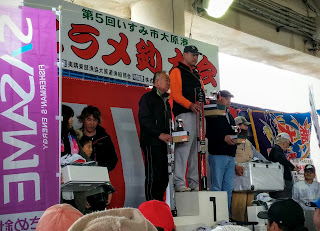中潮
ベニアコウを釣りに、南房和田港美智丸さんまで行ってきました。
昨年道具を揃え、相模湾で、3回ベニアコウにチャレンジしましたが、いずれもボウズに終わっています。
そう簡単に釣れる魚ではないのはわかっているのですが、今年こそはと。
アコウ・メヌケ類が釣りやすい、春分の日入りを狙っていました。
外房は黒潮の影響が強く、700号のオモリが必要とのことで、船宿指定の仕様で、600号オモリと100号オモリをビニールテープで巻いて制作しました。
予備のオモリとして、相模湾ベニアコウで使用した500号オモリ+手作り追加オモリ200号分を用意。
船宿指定の仕様のほうが、コストパフォーマンスに優れ、理にかなっていると思います
春分の日の日曜日は、あいにく休日出勤、仕事を終えた後、23時出発。
翌日(春分の日の振替休日)1時頃、和田漁港着。
仮眠後、5時集合次第出船。
釣り人は、私を含め3人。
深海900mを狙い、投入回数は4回。
仕掛けは投入回数分、事前に3日ほどかけて制作しました。
8本針枝1.5m、間4m仕様。25号ムツ針にタコベイトを追加。
昨年の反省を踏まえた仕様。
餌はイカの短冊、エンぺラを含めて縦切りに、2日前に仕込み、冷蔵庫で寝かしました
私の席はミヨシ。投入は大ドモからとなり、最後の投入。
南房は、新島キンメ、真鶴ベニアコウとは逆のようです。
どうも、投入の勝手が違う。
後でわかったのは、掛枠の針の向きを、逆にすべきでした。
ミヨシから、トモから、投入後、船が後退するか前進するかにより、巻き方も違うようです。
1投目は、餌を半分取られ、下のほうの針は、ハリスから食いきちぎられていました。
2投目は、まるでアブラボウズが釣れたかのように竿が曲るものの、竿が暴れず、とにかく重く、時折、釣力コントロールのグツグツとした動き。
上げてみると、2、3kgクラスのソコダラ類の3点掛け。(リリース)
3投目は、同じ仕掛け、餌を、マグネットから投入しようと試みるも、絡まり、船長に助けてもらいながら、なんとか投入。
ベニアコウの仕掛けは、枝も1.5mと長く、掛枠からでないと無理があるようです。
ラインを 950m~1050m出し、水深900mあたりの底を取ろうと、全長30m以上の仕掛けで探っていると、アタリらしきものが・・・。
大船長の合図で巻き上げ。
ドラグは、キツメ。
ここで、まさかの、リチウムイオンバッテリーがダウン。
船長から鉛バッテリーを借りて対応。
上げてみると、針の中盤で、赤いものがついてきました。
やった!、初ベニアコウゲット!
3.6kgでした。
ムツ針25号、下田漁具蛍光オレンジのタコベイト1/3割りにヒット。
4投目は、アタリなしで終了。
アコウダイとベニアコウ(オオサガ/サンコウメヌケ※)の違いは、釣れる水深と、重量。
6kgを超えれば、明確なのですが、3.6kgでのアコウダイとの見分け方を調査しました。
体形は、ずんぐりとしたアコウダイに比べ、細長くスマートな外観。
クーラー内寸70センチなので、
65センチくらい?
ずんぐりしています。
黒灰色の斑点が目立ちます。
眼の下を指でなぞっても、アコウダイのような棘はありませんでした。
味については、2日寝かしてから試してみようと思います。
<釣果>
ベニアコウ(オオサガ/サンコウメヌケ)3.6kg1匹
ソコダラ類イバラヒゲ、ムネダラ等2、3kgクラス3匹
<釣具>
リール:ミヤマエ CZ-9 12V
竿:ミヤマエ Vパワーマリアナ210VL(MAX500号負荷だが700号オモリも問題なく利用できました)
8本針、ムツ25号、幹糸40号、ハリス20号
枝1.5m、枝間4m
捨て糸:12号
ラインシステム:シマノパワープロPE8号下巻80m+PE10号1600m+リーダーPE20号を電車結び&編込みで連結。
金具:サルカンWBB9号1個。
(ヨリトリリング、チェーン、中オモリの類は、底立ちに不利と考え外しました)
オモリ:700号(鉛600号+100号をビニールテープで連結)
水中ライト:ミヤフラッシュカプセルFK207、前後をナイロン40号+ダイニーマノットで強化したラインで連結。
餌はイカの短冊、エンぺラを含めて縦切り。
ロッドキーパー:ラーク16
マグネット:
自作品ヒノキ80センチ長、ネオジウム6.5センチ間隔11個
(ベニアコウでの投入としての利用は不可。回収時用。)
バッテリー:PRPOX LIB-10400 3投目でダウン。
※ ベニアコウ(オオサガ/サンコウメヌケ)
ベニアコウとは、標準和名のオオサガおよびサンコウメヌケ。
2003年ロシアで、サンコウメヌケをDNA分析したところ、オオサガと全くの同一種であり、成長段階による(若魚)との論文が発表された。
サンコウメヌケという標準和名は、論文以降10年経った現在も健在で、その違いは口内が白いのがオオサガ、黒いのがサンコウメヌケ。
私が釣ったのは、口内が、アコウダイと同様に黒が混じり、やや灰色でした。
あえて、区別するなら、大きさ、関東で釣れる頻度からみても、サンコウメヌケ。
オオサガ、荒神(コウジン)メヌケは、もっと北のほうに生息するそうです。
いずれ、ヒレグロメヌケとともに、親潮の影響を受けたメヌケにチャレンジしたいと思います。